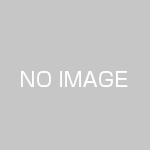- ホーム
- ウミガメの独り言(黎明編)
- タイマイ(No.6)
タイマイ(No.6)

タイマイという「言葉」には、奇妙な響きを感じる。僕の人生はタイマイとアオウミガメという二つの言葉を引きずっている。最近は、オサガメなどという言葉もちらほらと見え隠れしている。僕がタイマイと言う言葉を身近に感じたのは25年も前のことだ。 べっ甲屋さんが、タイマイ養殖の可能性を求めて、小笠原のアオウミガメの視察に大挙してやって来た時だ。この時以来、僕にタイマイという言葉が張り付いてしまっている。タイマイの産卵巣をみたのは20年以上前のことだけど、産卵をみたのはごくごく最近の1997年のことだ。実際にタイマイに関わりだしたのは1995年、インドネシアのタイマイ調査をやりだしてからだ。
僕が、いわゆる人が利用している生物の管理に対して、自分の進むべき道を決めたのもタイマイに関わったからだ。小笠原時代のアオウミガメの調査や人工ふ化などの事業は、自然保護という言葉を使って、結果としてオブラートに包んでいたと思う。”conservation”が日本では保護と訳されているが、今の日本の自然保護活動をみるとそれは決して”conservation”ではない。どちらかというと”protection”だ。”conservation”には「保護と管理」という意味がある。その意味での保護である。従ってこの単語のベースには人の経済的な活動があり、保護というのはその野生生物の適切な管理のことである。
日本がタイマイの輸入禁止をしたのは1992年からで、それまでインドネシアは世界最大の日本へのべっ甲材の輸出国であった。べっ甲屋さんは、そのため代替え品の開発や転職、再輸入の模索を始めた。それに付随して、インドネシアやキューバ、パラオなどでタイマイ資源の調査が開始された。調査は日本のアセス会社が行ったが、僕はその報告書をみるたびに怒りを感じる。また、べっ甲材の再輸入に関して、ロビー活動や資源量推定のモデルを使っていい加減な可能捕獲量を推定して、再輸入を図っていることにもさらなる怒りを感じていた。タイマイが輸入禁止にされたのは、あくまでも日本が無秩序にべっ甲材を輸入して、日本にはほとんど生息していない世界のタイマイ資源を絶滅寸前にまで減少させたからである。これは日本政府の問題なのである。日本が再輸入をする条件は、タイマイ資源量推定をしっかりと行い、利用できる状況にまで資源をしっかりと増やすことである。こんな事は誰にでも理解できることだけど、理解している人は日本にはほとんどいない。
続きを読む