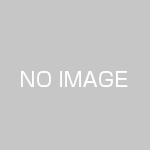- ホーム
- ウミガメの独り言(黎明編)
- 僕らのできること、気づくことの大切さ(No.39)
僕らのできること、気づくことの大切さ(No.39)
8月に小笠原に行った。全く進まない台風12号のおかげで、予定していた調査も全く進まない。その反面、新しいことに気づかされた。父島の南西にジョンビーチという海岸がある。スナガニによるカニ害や水没でふ化がほとんどみられなかった海岸だ。1980年代は年間5巣くらいしか産卵がなかったのだが、この約500個の卵からわずか3頭くらいの稚亀しか海に入れなかったのである。それが、近年になって産卵巣数が増えてきて、今年はふ化率が60%以上の産卵巣もみられるようになった。ジョンビーチに限らず、カニ害の多かった海岸でもカニ害率が低下している。なぜ、ふ化稚ガメが生産されるようになったのだろう。逆に、風光明媚な南島の海岸では、これまでほとんどカニ害がなかったのだが、今年になって急激に増加した。
話は変わるが、小笠原では、産卵された卵の場所を探すのに、建築材の鉄筋を使用している。産卵時に卵は親ガメによって踏み固められる。鉄筋を使用すれば、最初は柔らかく、奥に入るにつれてだんだん砂は固くなり、卵の間近まで刺すと急にスポッと抜けたようになる。そのスポッのスで鉄筋を止めれば卵を割らずに済む。しかし、これがなかなか難しく最初のうちは卵を割ったことすら分からない。また、サンゴダストや砂利石だとさらに困難度は増す。世界的にみると、鉄筋を使って卵を探すのは、卵を密漁する人たちだけである。彼らは、わざと卵を割って卵のありかを探すのである。小笠原以外では、産卵を観察して卵の位置出しをするが、小笠原の様にポケットビーチと呼ばれる小さな浜が50か所もあり産卵地では、全部の海岸に人を毎晩張り付けるのは不可能であり、全体の産卵巣数を知るために鉄筋を使った調査方法をとっている。
再び話が変わるが、父島の町のすぐ脇に大村海岸という海岸がある。この海岸は街の明りによって、ふ化稚ガメが海に行かず街の方に行き、側溝に落ちたり、車にひかれたりするため、やむなく卵の移植を行っている。当然、移植には様々なリスクが伴うわけだが、性比の偏りという最も大きなリスクを回避するために、性が決定された後に移植している。産卵後35-45日後である。このようにリスクを考慮して移植をしている例は、他の場所ではまだ聞いたことがない。これまで移植するときは、卵の位置をメジャーで確認して、穴を掘り、穴の中に手を突っ込んで、指の感触で卵を一つずつ取り出して、発泡スチロールの箱に移動して移植をしてきた。
続きを読む今年、大村海岸の移植をしたときに、何気なく穴を大きく掘ってみた。卵の表面が現れた瞬間、僕の目の前の世界が急に開けたのである。そこには、さまざまな世界が広がっていたのである。これまでは、手を穴の中に突っ込んで手探りで卵を取り出していた。それが、目で見ながら卵に触れることができるのである。当然のことながら、穴を大きくすることは、砂を取り除く作業量が格段に増えることになる。頭の中では、当然のごとく時間がかかる能率の悪い作業と判断される。しかし、実際には計り知れないメリットがそこには存在したのであった。現実的には、人さし指で卵の周りの砂を慎重にどけて卵を取り出していたのが、卵をみながら卵を簡単に取り出せるので、想像に反して時間的にも短縮されることになった。また、この時期に砂に接しているパンパンに膨れ上がった卵を割る確率も大きく減少する。まず、目に飛び込んでくるのは、卵室にある卵の立体的な存在感である。稚ガメがふ化するときに重要な空間、つまり卵と卵の間の空間、稚ガメがふ化して羊水が流れ出した分の空間、その空間の存在感が僕の頭の中に飛び込んでくる。次に気になるのが、鉄筋で突かれて破卵した卵である。破卵した卵はきれいに鉄筋の穴が開いたり、側面がスパッと直線的に割られたりしている。破卵した殻自体は少し厚みがあるがきれいな白色をしている。割れた卵は、周りの卵がほかの部分で何か所も接していて卵の重量が分散されているため、破卵した空間に転がったりしない。破卵の下には、明らかに死亡したと分かる茶色く変色した卵が縦に並んでいる。これは、破卵により中身が下の卵に粘りつき、呼吸ができなくなったためだ。横の卵には影響を与えていない。卵をある程度取り出すと、卵室のさまざまな場所にカニの穴があいている。上の方から、側面から、中には下から入り込んだカニ穴が開いているのである。また、必ずしもカニ害卵がカニ穴の出口のところにないことにも気づく。カニも卵の空間を利用して、食べやすい場所に移動していることが判る。カニ穴の大きさにも特徴がある。これは重要である。何故なら、ジョンビーチでカニ害率が減少したのは、海岸の砂が1m近くも消失したことにより、波打ち際付近の岩が露出し、海を漂っていた稚ガニが上陸しにくくなったためである。一方、南島でカニ害率が増加したのは、大きな台風が来襲したためである。つまり、高波によって、これまでほとんど生息していなかったスナガニの稚ガニが波とともに海岸に打ち上げられたと考えられる。その証拠にふ化率調査の時の産卵巣内のカニ穴は小さく、ジョンビーチの様なカニ害により全滅した産卵巣もない。カニ害は1巣につき数個のレベルなのである。このような海岸ごとの物語が見えてくる。大村海岸での移植時のちょっとしたきっかけが、物の見方を変えてくれる。自分の目で見て、手の感触のちょっとした違いが、いろいろなことを気づかせてくれる。現場にいなければ、こんなことは気づかないし、現場にいても日々の変化を意識していないと気づかないのである。気づくということには、常に疑問を意識しているかどうかが前提となる。海岸にいて、気づくことがなくなった時が、きっと僕のカメ屋としての終焉なのだろう。(「僕らのできること、気づくことの大切さ」了)