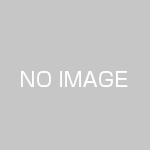- ホーム
- ウミガメの独り言(黎明編)
- 生きたデータ(No.37)
生きたデータ(No.37)
先週土曜日(5月28日)、フリーダイバーの平井美鈴さんとELNAのコラボでトークショーを行った。終わった後、懇親会をやったのだけど、参加したほとんどの方は平井さん関係の人が多かった。でも、僕がちょっと驚いたのは、何人もの人がELNAのホームページのこの「ウミガメの独り言」を読んでくれていたことだ。これを聞いて僕は深く反省をしている。この原稿も実は5カ月ぶりで今年2つ目だ。昨年は全く書いていない。2009年は6つくらい。
現在、横浜事務所に3名、小笠原事務所に5名のスタッフがいる。インドネシアには4名のスタッフと30名ほどの監視員。8月には横浜事務所のスタッフが1名増える。内部もようやくまとまってきて、スタッフも前を向いていてくれている。これから、ELNAがステップアップしていくには、僕自身のテンションを上げていかなければならない。この「独り言」はそのための僕のステージなのかもしれない。これからは書くことを僕自身の自責の念として、自分自身に課していこうと、密かに思うのである。これを読んでELNAの会員になってくれる人もいるかもしれない。ウミガメの現場や現状をもっと知りたいと思う人も出てくるかもしれない。僕らは、現場の見えない声を大にして、訴えていかないといけない。ELNAの存在意義をそこに置きたいと思う。
アメリカとの確執は、昔このコラムで書いたと思う。「オサガメの資源回復と保護を目的としていながら、アルゴス追跡と産卵巣のモニタリングだけで、なんでオサガメが増えるんだ。どうして守ることができるんだ。」こう言って、僕はアメリカに喧嘩を売っていた。いや、喧嘩ではない。僕の素朴な疑問だ。人が取った数値、画面に出てくる緯度経度の無味乾燥な数字、ほとんどのウミガメの研究者はこれらの数字を使って、報告書や論文を書いている。ハワイにジョージ・ボラージュという米国海洋漁業省海洋科学部門の人がいる。日本も含め、アジアにウミガメの調査のために多くのアルゴス発信機を送ってくれている人だ。小笠原でも2008年にタイマイのアルゴス追跡のために送ってもらったことがある。アルゴスのデータは、緯度と経度が並んでその横にそのデータの信頼度がAとかBとか、信頼するなというZとかいうランクがついて、毎日ドバッ、ドバッと、コンピュータの画面に衛星の会社が送ってくれる。全く無味乾燥な数値である。ところが、ジョージはこのデータに息を吹き込んでくれる。緯度・経度を地図上に落とし、定期的にその地図を送ってくれて、コメントを入れて夢を与えてくれるのである。アルゴスのデータで、僕は彼からデータの温かさを知った。
続きを読む