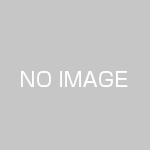豊橋市にふ化場ができているらしい。それを推進している団体もあり、反対している団体もあると聞いた。両方ともウミガメの保護団体らしいが、ウミガメやその環境を保護するための目標は同じだと思うのだけど、どうして正反対の施策が出てくるのだろうか。パプアでも、2003年10月に津波があり、砂が大量に消失し、波が被りやすくなり、ふ化率が極端に落ちた。ふ化率が5%にも満たない時もあった。僕らは、それを見守っているだけだ。ところが、アメリカはそれをみて2006年から移植試験を始めた。僕には何のために彼らが移植試験を始めたのかが理解できない。直接彼らに聞いてみると、当然のごとく「オサガメは減少していて、ふ化率が低いからだ。だから移植試験をする。」と言う。「なるほど。」なんて、僕はうなずけないのだ。彼らが移植してもせいぜいシーズン中に100巣程度だ。全体の6%程度である。パプアでは全卵移植するようなシステムを作り上げることは不可能である。これだけでも、何のために移植試験が必要なのか、僕にはよく分からない。ウミガメを守るために、何をすればよいかという命題は、非常に難しい問題である。つまり、ウミガメの保護の根幹に関わる問題だからである。ウミガメを守ると言うことは、繁殖地に限ってみれば、その海岸環境を守ることに繋がる。ウミガメ単体だけを守るなんてことはできない。ウミガメを守っても海岸がなくなれば、ウミガメを保護したことにならないからである。
カメを増やす、絶滅から守る、という活動には、必ず基準が必要なのである。比較するものがなければ、本当に増えているのか、絶滅を回避できているのか、全く分からないからである。産卵巣のモニタリングだけでその結果を知ろうとすると、少なくとも30年くらいはかかってしまう。その基準となるものが、カメの場合は海岸である。
津波があって、海岸の砂がなくなり、ふ化率が落ちるというのは自然現象である。現世のカメは400万年以上も、その種を維持してきている。オサガメに至っては、その直接の祖先は8000万年も前に誕生している。当然の事ながら氷河期や間氷期の厳しい温度差も乗り切って、種を維持している。津波など腐るほどあったに違いない。ウミガメの種によって、産卵海岸を変えたり、産卵位置をオープングランドにしたり、海岸後背地の草付きの中にしたり、その境目だったり、様々な戦略を採っている。
続きを読む
僕は、ウミガメを海岸環境やその変化を知ることのできる指標動物として位置づけている。ふ化しなかった卵の状態により、高波による水没のため、砂中温度が高いため、様々な動物による食害のためなど、ふ化しなかった卵はその死亡要因を如実に表す。水没により死亡した卵の出現率を追うことにより、砂の消失や堆積状況を知ることができる。パプアでは、その率が減少しており、ふ化率も昨年当たりから、急激に上昇を始めている。僕らは、現状をあらゆる角度からみて、データを取り、カメのおかれている周りの環境状況を把握することしかできない。砂は増減を繰り返し、カメの資源量も同様に増減を繰り返す。また、現在起きているウミガメの減少要因は、そのすべてと言ってよいほど、直接的・間接的な人間行為によるものだ。ウミガメの種や海岸によってその対策はすべて違ってくるが、ウミガメを増やすのには、ウミガメを指標動物と見てデータを取り、ウミガメに悪影響を与えている人の活動部分を取り除くことしかできない。人により持ち込まれた動物による食害を減らす。海岸に流れ着いた巨大な伐採木を排除する。人は、そんなことしかできないのだと思う。
話を戻すと、日本の海岸の場合、すでに自然海岸はほとんど残っていない。海岸には人工物があり、川のダムは海岸の砂の供給を停止する。そのような海岸にカメが上がってきた場合どうするのだろう。海岸はどんどんやせ細り海岸自体が消滅する。その前にふ化率はどんどん減少していき、最終的にはゼロになるだろう。日本のほとんどの地域において、ウミガメを守るというのは、そのままダイレクトに海岸を守ることに繋がり、そうしなければウミガメ保護は成り立たない状況になっている。近い将来に海岸がなくなって産卵できない状態が予測できるのに、そのような海岸のウミガメをなぜ守らなければならないのか。堤防やダムのことを除外して、海岸保全を考えることはできるのか。自然状態で海岸の評価指標となる産卵巣の流失率や冠水率、食害率、ふ化率の長期にわたる解析なくして、ウミガメの保全ができるのか。ただ漠然と、ふ化率が低くそうだからと言って、安易に卵の移植を行ってよいのか。僕の知る限り、卵の移植をしてウミガメ資源が増えた例は世界中にない。例え、移植のふ化率が自然状態の2倍あったとしても、次世代の生産量は半分になることが理論上分かっていても、なぜ移植をするのか。現実的には、日本において、移植しているところのふ化率は、自然状態の平均ふ化率と比較してもほとんど変わらないのが実状であるのに、何のために移植を行うのか。信じられないことだが、ふ化率が高いことを示すために発生していない卵を除いて、独自にふ化率計算をしている団体まで存在する。何のためにそんなことをするのか、全く理解できない。行政はただ予算消化のためにふ化場を建設するだけなのか、それともふ化場が本当にカメを増やす手段であると信じているのか。カメの世界は、分からないことだらけである。(「人は何のためにウミガメを守ろうとするのだろうか」了)