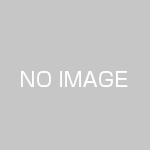- ホーム
- ウミガメの独り言(黎明編)
- 混沌とした調査の行き着く先(僕らはちゃんと歩いていけるのだろうか)(No.21)
混沌とした調査の行き着く先(僕らはちゃんと歩いていけるのだろうか)(No.21)
明日(2007年2月2日)から、インドネシアに行く。前回の「ウミガメの独り言」も、この出だしで書いた覚えがあるが、前回の時は出発当日の夜中に入院し、行くことができなかった。本当は、この出だしを書くのを躊躇している。また同じ様なことが起きないかという恐れがある。
このところ、海岸で調査をしているといろいろなことが頭に浮かんでくる。浮かんでくるという言い方は少しニュアンスが違う。頭の中に形が見えてくるのである。気が付いてしまうのである。僕らの調査は歩くことが主体で、海岸やカメをみていると、それらの状況に僅かな違いが見えてくる。幅の狭い海岸を歩いていると、狭い檻に入れられた様な圧迫感がして、同時に荒れた時の波が打ち寄せる状況が浮かび、卵の水没に結びついていく。前回、イリアンジャヤのマノクワリというところに行った。ここもオサガメの産卵地である。最初、海岸が狭いことによる窮屈な感覚が僕を襲ったのだが、オサガメの産卵跡を見たとたんに、すっーと、その窮屈さが消えたのである。消えただけではなく、ホワホワした暖かさを感じた。これまで、オサガメの産卵巣は広い幅を持つ海岸の真ん中にあるのが、僕の頭の中では当たり前になっていた。オサガメの産卵巣は、グンバイヒルガオの草の中にとけ込んでいる。初めてみたその情景に、思わず足が止まる。オスの割合の高さ、目の前の太平洋に生息しているオサガメにとってこの海岸の存在がいかに重要か、ふ化率の安定している様子、人知れず産卵するオサガメの様子、卵の存在感、そんな海岸に今いることの安心感などなど、様々なことが機関銃の弾丸のように僕の頭の中で次々と弾ける。さらに、食用のために屠殺されたアオウミガメの甲羅、卵が持ち出された産卵跡、そこに住む人々の様子も、かいまみられる。海岸も、森も、カメも、人も、その鼓動が聞こえるようである。
僕らの仕事は、海岸にいるときは一対一の勝負である。周りのしがらみとか、清く正しいデータの取り方とか、そんな気持ちは全くない。その時に自分の目で見ていることだけが、真実なのである。砂の盛り上がり方、足跡の様子、産卵雌ガメの息づかい、標識を装着した瞬間の清らかさ、18kmの海岸に50mおきに番号札を木に取り付けるときの少しずつ高まる気持ち、電気柵が完成したときの押さえつけようのない高揚感、ふ化率調査で卵を割ったときの抜けるような感覚、だけど、これらは決して動物に感情移入しているわけではない。最近読んだ本で、僕と同じように感じている人がいることを知った。少し長いけど、引用してみたい。この本には、生物の40億年間の記録を書いてある。この引用文章の前は、まさに動物が陸上に進出しようとする古生代のデボン紀が舞台になっている。
続きを読む